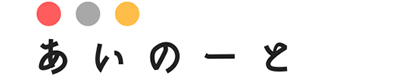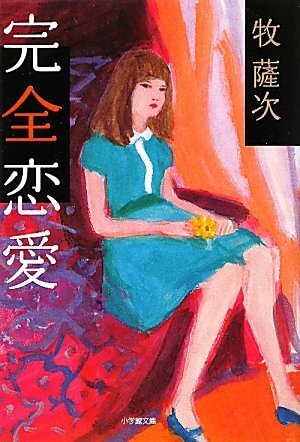読むことで絶望感や、やるせなさを感じる本は何のために存在しているのだろうか?
読後感の悪い本を時間をかけて読み、不快感を感じるメリットについて僕はよく考える。
貫井徳郎『乱反射』を読んだ時も同じように悩み、苦しんでしまった。
この作品は何人もの人間が、罪とも呼べぬような小さな罪・・・時間つぶしの為の反対運動や犬のフンを放置した程度の罪が重なって起こっていくことで、一人の幼児の命が奪われてしまうというストーリ―になっている。
救いの少ない辛い話。
嫌な気分になる話。
なぜそんな本を読むのだろうか。
今回はこの作品のネタバレ感想と悲しく救いの少ない話を敢えて読むことの意義について書いてみたいと思う。
乱反射
あらすじ
幼い命を死に追いやった、裁けぬ殺人とは? 街路樹伐採の反対運動を起こす主婦、職務怠慢なアルバイト医、救急外来の常習者、飼犬の糞を放置する定年退職者……小市民たちのエゴイズムが交錯した果てに、悲劇は起こる。残された新聞記者の父親が辿り着いた真相は、法では裁けない「罪」の連鎖だった! モラルなき現代を暴き出す、日本推理作家協会賞受賞作、待望の文庫化!(引用|amazon)
第一章、第二章・・・と進んでいくのではなく、-44からカウントダウンしていき、0になることで悲劇が起きるような章の構成になっているのが象徴的。
場面の移り変わりが激しいので、人によっては事故にどのように関わるかわからないような人物たちの日常の話が続く前半部分をかなり退屈に感じるかもしれない。
しかし、中盤以降はそれぞれの登場人物の関わり合いが強くなっていき、物語の悲劇の結末に対する嫌な予想が少しずつその姿を現していく様子に、知らず知らずページをめくる手に力が入ってしまう。
そして終盤では子供の死に対して父親が調査を続けていき、最後には怒りがやるせなさに代わって物語が終焉を迎えることになる。

感想
誰でも経験がある小さな罪。
道端にごみを捨てたり、歩きたばこをしたり、電車の中で化粧をしたり。
罪とも呼べないようなルール違反・・・というよりモラル違反が連続することで巻き起こる悲劇が描かれている作品。
亡くなった幼児の父親は新聞記者で、わが子が亡くなった原因について追求していく。
やり場のない怒りを内におさめつつ子供の死に絶望する妻と死に向き合っていく様子はやるせなさしか感じない。
新聞記者である父親が、直接的な原因を作った樹木の管理会社の職員だけではなく、その職員が樹木を触れなかった原因である犬のフンの放置を行った人物や、責任がかからない立場で樹木伐採の反対運動をした人物を訪問していき、どうしてこんな事故が起きたのかを探っていく。
しかし、出会った人物すべてが、
「わたしは悪くない」
という責任転嫁の言葉を口にするばかり。

その責任のなすり付けは人間の嫌な部分が凝縮されたような印象を受ける。
謝ること自体が間違っていると突っぱねて、自分の行為を正当化しようとする様子は、読んでいると気分が悪くなっていくほどだ。
もちろん、彼らの言い分もわかる。
ただ犬のフンを放置したからといって、そのせいで子供が死ぬなんて誰が思うだろうか。
自分が悪くないと言いたくなる気持ちも理解できてしまうのだ。
ただこの小説は、そんな小さな罪を糾弾することを目的としたものではないのだと思う。
僕が思うこの作品のメッセージは、
しょせん人間なんてみんな同じ穴の狢だよ
ということだと思っている。
モラル違反を犯した登場人物も。
子供を失った夫婦も。
それこそ読者や作者でさえも。
太宰治『晩年』の一節を引用するならば、
「自信モテ生キヨ 生キトシ生クルモノ スベテ コレ 罪ノ子ナレバ」
ということ。生きとし生ける者は全て罪の子なのだ。
結局人間は生きていく中で小さな罪やモラル違反を犯しながらでしか生きていけないものなのだろう。
作品の中に問題提起を盛り込んだこういった作品は、たとえ読後感が悪かろうと多くの人に読んでもらいたいところだ。

ラストの場面
この作品でもっともメッセージ性が強い場面はラストシーンだ。
他人のモラル違反が連続したことで愛する子供が死に至ってしまった主人公の父親。
小さな罪だろうと、そのせいで子供が死んでしまったことは事実なので、その小さな罪も許さずに戦う姿勢を見せていた父親だったが、過去に自らもルールを破ってゴミを捨てていたことを思い出してしまう。
そして自分自身も同じ穴の狢であったことを自覚し絶望して終わっていく。
小さなモラル違反を自分も犯していたことで、子供を殺していたのは間接的な自分であり、他人を責める資格が自分にはないことを自覚するのだ。
父親の絶望感と慟哭が目に浮かぶような悲しいシーンだ。
読み方によっては、読後感が悪く絶望しかない終わり方ともいえる。
しかし、長い目で見たら、あのラストシーンは救いなのではないだろうか、と僕は思う。
ごみを捨ててなかったら自分たちは清廉潔白な人間として、ずっと仮想の敵を恨み続ける人生を歩むことになる。
そんな圧迫された人生は果たして幸せなのだろうか。
この両親は、自分たちだけが清廉潔白なわけではないということを受け入れることで、他人を許せるようになるのではないだろうか?
最後の沖縄旅行でほんの少しだけ諦めたというか、子供の死を受け入れたようにも思える。
その様子は、絶望の中に見えた諦めの許しだと僕は理解することにした。
最後に
本当に絶望的で、やるせない作品だった。
なぜこういった作品が世に生まれ、人々が手を伸ばすのだろうか?
もしかすると、時にこのような作品を読むことで対比するように自らの人生に希望を見出すことも出来るようになるのだろうか。
ただ、現実が理不尽なことはもう知っている。
だから創作物までそんなに理不尽にしないで欲しいな、と、ただただしんみりとそんなことを思ってしまう。
今はただ悲しい。