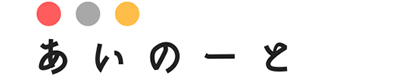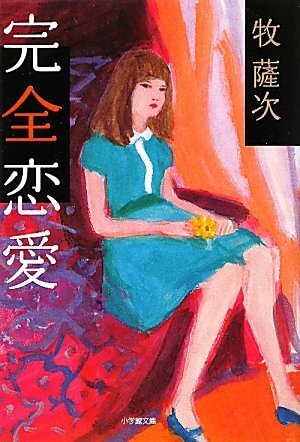奇をてらった題名で注目を浴びようとする作品はほぼ間違いなく駄作である。
基本的にはそんなスタンスを持っている僕は、あまりにも攻めた…というより狙ってんなぁと感じてしまう題名の本を手に取ることが少ない。内容に自信がないからタイトルだけでも狙いにいっているように感じるからだ。
今回の本『人間の顔は食べづらい』も、奇をてらったタイトルの作品だったため、あまり期待せずに読み始めたものの、奇抜なタイトルと舞台設定に飲み込まれることのないロジカルな推理と鮮やかな逆転劇を見せてくれる良作であった。僕と同じくタイトルでこの作品を敬遠している方々へ、この作品の魅力を伝えると共に一部のネタバレ感想を書いていきたいと思う。
人間の顔は食べづらい
あらすじ
世界的に流行した新型ウイルスは食物連鎖で多様な生物に感染し、爆発的な数の死者をもたらした。ヒトにのみ有効な抗ウイルス薬を開発した人類は、安全な食料の確保のため、人間のクローンを食用に飼育するようになる。食用クローン人間の飼育施設で働く和志は、自宅で自らのクローンを違法に育てていた。
ある日、首なしで出荷されたはずのクローン人間の商品ケースから、生首が発見される事件が発生する。和志は事件の容疑者とされるが、それは壮大な悪夢のはじまりに過ぎなかった―。異形の世界で展開される精密でロジカルな推理劇。第34回横溝正史ミステリ大賞最終選考会で物議をかもした衝撃の本格ミステリ、解禁。(amazon)
感想
人間が人間を食べる行為、いわゆる“カニバリズム”が認められた近未来のミステリー作品。とはいえハンニバル・レクター博士のような異常者としての食人行為ではなく、食糧確保のために、自身のクローンのみを食用として飼育して食べることが法律的に許されているという条件付きの世界が舞台になっている。作中では二人の視点から交互に物語が語られていき、二つの視点が交差するとき、大きな驚きと共に物語が鮮やかな終焉を迎えることになる。
もちろんカニバリズムが法律的に許されているという特殊な設定ではあるが、その限定条件に寄りかかって内容がスカスカな訳ではなく、しっかりと伏線を生かしたサスペンス&ミステリーになっている点が一番評価されるべきポイントではないかと思う。大賞こそ逃したものの、第34回横溝正史ミステリ大賞最終選考に残り、有栖川有栖氏、道尾秀介氏から強い推薦を受けたのも納得の作品といえる。

自分自身の細胞から作られたクローン人間であったとしても、その生命体を殺処分して肉として食べると言うのは、他ではあまり味わえない独特の嫌悪感がある。他人の肉を食べるよりも自分自身の肉を食べる方が抵抗が少ないという感覚もわからなくはないが、やはり読んでいて気持ちのいいものではない。その嫌悪感はやはり人間を食べるという行為そのものから生まれるものなのだろう。
食料としての人間
ミステリーとしての魅力。仮想未来のSFとしても魅力。それだけではなく、この作品では、
「人間が人間を食べることの何が問題なのか?」
ということを読者に考えさせる点も作品としての大いなる魅力といえる。

「倫理的に良くない」と言うのはとてもずるい言葉だ。その事象について、さも社会全体が問題視しているかの様に感じさせることができる。倫理的に良くない要素が1mmでも入っていれば、言ったもん勝ちのようなズルい言葉、無敵の思考停止ワード。それが「倫理的に良くない」という言葉だ。
が実際のところ、人が人を食べる行為の何が問題なのかと問われると「倫理的に良くない」という理由以外で、僕は誰しもが納得のいくような答えを用意できない。もちろん、まったくもって食べたいわけではないのだが、単なるディスカッションとして、明確に相手に納得してもらえるであろうカードを僕は持っていないのだ。

例えば、殺人行為を伴うカニバリズムは殺人という行為に正当性がないので納得させられると思う。また、食用としてクローン人間を生み出すという行為については、“人間”という言葉の定義を議論すればいい。クローンであれ人間は人間だという結論になり、やはり殺人行為を伴ってしまうことを伝えられるはずだ。
しかし、例えば亡くなった人間を食べるという行為については、明確な反対理由は持てない。民族によっては、族内食人といって仲間内で死んだ人間を食べる部族もあると聞く。故に倫理的な視点を除いた場合、カニバリズムが否定される理由はないのではないかと思う。強いて挙げるなら・・・というかこれが最大の否定理由ともいえるが、生理的に嫌だという感覚的な拒否反応が一番の障害だ。

ただ、生理的に嫌だという理由は、例えば昆虫食などにも見られる生理的拒否反応とも似ているため、一般的な文化の違いとも言える。つまり長い目で見た場合、受け入れられていく問題のようにも思える。人間が人間を食べるという行為について、改めて問われることで今まで考えていなかったような考えに至ることは面白く。読んだ人間同士で議論が生まれることになる。当然その議論は、人間のクローンを生み出すこと自体の是非についてもされるべきだろう。
クローン技術
ちなみに僕はクローン技術を使って人間が生み出されることに関しての問題点は、同じDNA、もしくは指紋を持った人間が増えることによって個人が特定されず、犯罪捜査に困難をきたして犯罪率が上がることだと思っている。特に勝手に他人のクローンを作成して犯罪に利用することで冤罪を容易に生み出すことが出来る。また、完全に個人が特定されない限りは犯罪を立件できないという不具合もある。
あとは、言葉の定義の問題ではあるが、クローンで生み出された人間のことを自然に生まれた人間と同じ権利を、法律上で取り扱うべきなのかどうかといった権利上の問題もある。戸籍上の生みの親は誰になるのか。もしくは単独で籍が発生するべきなのか?それに伴い結婚・出産など多くの事務手続きに対応が迫られ、社会的に大きな混乱が起きるのではないか。
ただし、興味があるという1点のみを考えるのであれば、自分と全く同じ細胞を持った人間を子供の頃から育てることができるのであれば、それはそれでとても面白い感覚を味わうことができる。可能であれば試してみたいくらいだ。
また優秀な遺伝子を持つ科学者スポーツ選手などのクローンを残しておくことで、人類の発達のスピードは飛躍的に上がるのではないか。(同時に滅亡も早まるような気もするが)要するにクローンという技術そのもののが問題なのではなく、その技術をどのように活かしていくのかという点についてこの作品は大いに考えさせられる内容となっているということだ。技術は技術だ。問題と混合して考えるべきではない。

カニバリズム作品
生理的嫌悪感を覚えるのと共に、描写によっては背徳感すら感じさせる禁断のカニバリズム。多くの小説にそういった描写が描かれていることから、人間に与える衝撃度の大きさを改めて感じる。有名作品をいくつか見ていこう。
上記したが、トマス・ハリス『羊たちの沈黙』『ハンニバル』に登場するハンニバル・レクター博士は、人間の頭部をカットして生きたまま脳みそを焼いてディナーにしていた。小説の世界の食人鬼として一番有名な存在かもしれない。
もちろん、日本にもそういった作品は多数存在する。平山夢明『独白するユニバーサル横メルカトル』の中の小編『Ωの正餐』では、ヤクザが死体を処理するために人間に人間を食べさせるという仕事としての食人行為。行為自体は気持ち悪いが、語りが面白いので嫌悪感は小さく面白い作品だ。
また、綾辻行人のような有名作家が食人行為を描いていることもある。『十角館の殺人』をはじめとする館シリーズの集大成的作品『暗黒館の殺人』では、ダリアの宴と呼ばれる会にて塩漬けされた人間の肉をスープに、血をワインに、骨はパンのペーストとして食べる描写がある。暗黒館の粘着質の暗闇にマッチする演出ではあるが、やはり読んでいて気持ち悪い。
トム・ロブ・スミスの『チャイルド44』も小説ではあるが、旧ソビエト連邦ウクライナのホロドモール大飢饉における当時の様子が描かれる中で、食べるための幼児誘拐が行われていた描写がある。作品自体はフィクションだが、史実に基づいた出来事を描いているように思える。
不思議なものだが、こういった作品を読み続けていると感覚がマヒしてくるもので、人間が人間を食べる描写を読んでいてもなんとも思わなくなってくるから恐ろしい。
最後に
でも人間は食べちゃダメ。