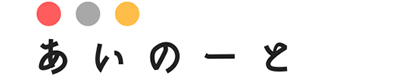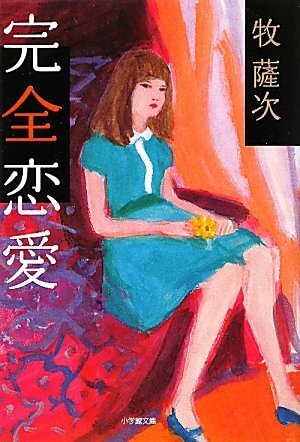先日、『スロウハイツの神様』を読み終えてすぐ、同じく辻村深月の『ゼロハチゼロナナ』を手に取った。スロウハイツを読み終えたあとの温かな感動と爽快感が忘れられずに、同じく辻村作品を読むことにしたのだ。ところが、その安直な行動で僕は大いに傷ついた。
この『ゼロハチゼロナナ』は、母と娘の確執の話。人が人に向ける悪意の話。そして母親を殺害して逃げる娘の話だ。温かな感動なんて甘っちょろいものはない。読んでいて辛くて辛くて仕方なかった。それでも最後には大いなる感動が待っている素晴らしい作品なので、今回はこの作品のネタバレ感想を書いていきたいと思う。
ゼロハチゼロナナ
あらすじ
事件を起こすなら、私のほうだと思ってた。母を殺してしまった娘と、母との確執を抱える娘。どんな母娘(おやこ)にも起こりうる悲劇。地元を飛び出した娘と、残った娘。幼馴染みの二人の人生はもう交わることなどないと思っていた。あの事件が起こるまでは。チエミが母親を殺し、失踪してから半年。みずほの脳裏に浮かんだのはチエミと交わした幼い約束。彼女が逃げ続ける理由が明らかになるとき、全ての娘は救われる。著者の新たな代表作。(amazon)
第一章の主人公・みずほは地元の交友関係を断ち新たな人生を送っていたが、幼馴染のチエミの殺人と失踪を知り、チエミの行方を捜すために様々な人と再会して話を聞いていく。チエミとその家族、特に母親とは合コン中にその相手のことを電話で報告するなど、周囲が気持ち悪さを感じるほど仲が良かったので、何故チエミが母親を刺し殺したのか、そしてそのチエミ自身は無事なのかを確かめるためにみずほは行動を起こしていく。
第二章ではチエミの視点での逃亡生活が描かれており、第一章でさまざまな憶測にさらされていたチエミの行動の謎と事件の真相が描かれている。逃亡中に起きた出来事や、出会った新しい人間関係を読むことで第一章では知りえなかったチエミの人間が浮かび上がっていく。母親殺害というミステリー要素を主軸に謎を深める第一章とその答え合わせをしていく第二章というような構成の中に、
- 母と娘の関係性
- 女同士の友情
という二つの大きなキーワードを織り交ぜており、それらがこの作品の根幹になっている。

母と娘の関係は選べない
作品に暗い影を落としているのはみずほとその母親の関係性だ。幼いころからみずほの母親は、愛情と教育という大義名分を掲げながらみずほを虐待していた。ジャンクなものを勝手に食べたら極端に叱ったり、コーラを頭からぶっかけながら叱ったりと、直接的に暴力に訴えるような虐待ではなく、親の立場を利用した圧倒的優位からの理不尽な教育という名の虐待だ。
途中で判明することだが、母には虐待していたという自覚があり、それを占い師にだけ自己弁護を交えつつ相談をしていた。隠してあったそれらの手紙のやり取りをみずほが見つけて怒りに震える。そしてただ一言、「読みました」というメモだけを残して何も触れないで親元を離れた過去がある。もはや修復することが不可能な親子関係といっていいかもしれない。
対して、チエミとその母親は周囲の誰もが仲良しと認める親子関係だ。ケンカもせず関係も良好な理想的な親子関係にも見えるのだが、起きた出来事、出会った人のこと、何でもかんでも両親に話すという行き過ぎた情報共有が、単純に素敵な関係と呼ばれるそれを超えている印象も受けてしまう。
そんな良くも悪くも距離が近い親子だったのにも関わらず、どうして刺殺事件など起きてしまったのか?それはチエミが妊娠していると母親に打ち明けたことが関係しており、結婚していない状態での妊娠について、母親が許さなかった為の事件(事故?)であった。そして、殺人鬼の子供として生きさせないためにチエミは赤ちゃんポストを目指しているわけだが…そこは辻村深月作品。一筋縄ではいかない展開が待っている。
チエミの逃亡の理由が妊娠なのではと、作中ではずっと匂わせているが実際は妊娠していなかったという絶望。そして、チエミの母に対する依存は、実はみずほがチエミの母親を大好きと言ったことから生まれたという驚き。つまりは、チエミのみずほに対する強烈な依存から生まれた親子関係だったりということが判明する。想像していない感情の動きが物語の最後にたたみかけてくるので、今回も辻村深月に圧倒されてしまった。読んでない方の為に、タイトルの大きな謎についてはあえて触れないでおこうと思う。

女の友情
「チエの中に、自分を反射して見ないで」
殺人を犯したこととは無関係に、チエミへの悪意が語られる場面が多く描かれるのもこの作品の特徴かもしれない。いい子でいるチエミに自分自身を反映させて勝手にイラつく人物や、その存在そのものを軽く見て、騙しながら接したりする人物が多く、そういった人間たちから話を聞きながらみずほはチエミの行方を追って行く。
例えば、チエミの職場の同僚の亜理紗などがそうだ。
彼女は一見普通の、むしろみずほに似た常識的な人物ではあるのだが、話を聞いていくと徐々にチエミに対しての、イラつきが言葉の端々にとげのように現れてくる。みずほは初めこそしっかり話を聞いているが、最後にはチエミに為のウソをついて亜理紗を突き放す。読んだ時の感覚からすると、当初は亜理紗に好感を持っていたはずなのだが、途中から何故かその亜理紗の感覚に反感を覚えるようになっていくのが面白い。

最初から悪意全開のクソ野郎も登場する。チエミの元彼…と呼んでいいのか難しい所だが、チエミのことをもてあそんでいたクソ野郎・大地だ。彼が話す言葉は全てが悪意と優越感に満ちていて不快になる一方だ。
みずほはチエミを放っておいた罪悪感と、大地への怒りをエネルギーに変えてチエミを捜索していくのだが、とにかくこの大地から放たれる言葉がキツい。トゲなんていう生易しいものではなく、剥き出しのノコギリの刃のような言葉が大量に放出されていく。
「モテない女子たち。人生にちょっとしかイベントがなくて、それにしがみつくしかないなんて俺だったら耐えられない。かわいそうだな」
「だけど、あんたは言わなかった。今更親友ヅラして、悪者探すなよ」
「随分ご無沙汰だって言ってた。かわいそうに思って」
最低を通り過ぎてにじみ出る悪意に心が浸食されてしまう。最初から最後まで貫き通す、どこに出しても恥ずかしくないクズ男、それが大地だ。
それに引き換え、登場の印象と大きく違ったのは地元仲間の政美だ。
ギャンギャン喋るし、嫌味を言ってくるし、他人を罵るときに驚くほど語彙が豊富になる政美は、当初、結婚式に呼ばれなかったことを根に持ってみずほを敵対視している。厭味ったらしいことを言ったり、好戦的に接したりと良い印象なんてこれっぽっちもなかったのだが、結果的に照れ隠しの側面があったり、協力的に接してくれたりと、行動が変わっている訳でもないのになぜか好印象を覚えてしまった。女性同士の友情には、男には理解できない独特のコミュニケーションがあるのかもしれない。

最後に
この作品は、とてつもなく胃の府に負担がかかるストレスのかかる作品だ。
救いと呼べるような救いはほとんどないのだが、唯一、救いと呼べる出来事と言えば、絶望するチエミの元にみずほが間に合い、ただその人が存在しているという事に対して必死になってくれる人がいる事だ。
人は何もかもを無くして絶望したときに、必死になってくれる人が一人いれば、それだけで生きていけるものなのかもしれない。