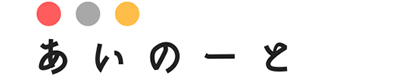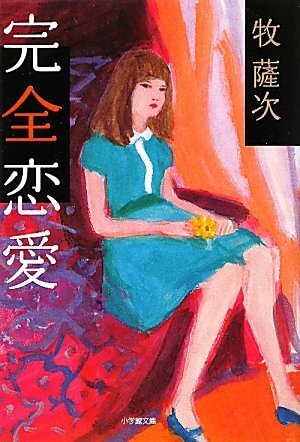有川浩『明日の子供たち』を読んだ。
多くの有川作品を読んできた中で、僕がNo1であると断言できる作品かもしれない。
いや、断言してしまおうか。
この作品がNo1だ。ハッキリ言って名作だ。
あまり強い言葉で褒めると作品のハードルが上がってしまうかもしれないが、読みやすくて面白いという有川作品の特徴を生かしつつ、スポットライトの当たりにくい社会問題を作品に仕上げたのは流石と言える。
今回はこの素晴らしい『明日の子供たち』のネタバレ感想を書いてみたいと思う。
明日の子供たち
あらすじ
三田村慎平・やる気は人一倍の新任職員。和泉和恵・愛想はないが涙もろい3年目。猪俣吉行・理論派の熱血ベテラン。谷村奏子・聞き分けのよい“問題のない子供”16歳。平田久志・大人より大人びている17歳。想いがつらなり響く時、昨日と違う明日が待っている!児童養護施設を舞台に繰り広げられるドラマティック長篇。
なんとなく抜けているような印象を抱く新任職員の三田村慎平が、児童養護施設の”あしたの家”にやってくるところから物語は始まる。
漠然と児童養護施設にいる子供たちの事をかわいそうな存在だと認識していた慎平は、施設のこざっぱりした現実に触れてその認識を改めていく。
また、施設にいる子供の久志や泰子の視点から見た進学やお金などの現実的な問題、職員たちの立場から見た子供たちへの葛藤などが描かれている。
重くなりがちなテーマを有川浩特有のリーダビリティの高さで、読書初心者が読んでも楽しめる作品に仕上げているのが素晴らしいと思う。
現場から支持される作品
この作品ではかわいそう子供たちがお涙頂戴なドラマを経て、幸せになるようなベタな話ではなく、あくまでも冷静に現状に向き合っている子供たちと職員の世界が描かれている。
ゆえに、特に業界の人間から評判がいいという話を聞いた。
児童養護施設の職員に、施設とはどんな場所なのかを聞いた時に、この本を読めば大体わかるよ、と言われた知り合いもいる。
業界にいる人間から見ても、内容と現実に差異がないのは驚きだが、なんにせよ、現場から支持される本は素晴らしいと思う。

”かわいそう”という糞ニーズ
作中では”かわいそう”という言葉がとてもデリケートに扱われている。
新任職員の三田村は良くも悪くも素直でまっすぐな人間なので、その”かわいそう”で痛い目を見た。
児童養護施設に入っている子供たちを、ただそこにいるだけで”かわいそう”という一言でまとめてしまい、そのことに怒った奏子から完全に一線を引かれて接せられることになってしまったのだ。
たしかに、施設の子供たちは”かわいそう”というイメージを世間に持たれている部分がある。恥ずかしながら、僕もそれに近い感情を抱いていた。
しかし、直接現実を見ずにイメージだけ先行して憐れまれるなんて、当事者にしてみたらたまらないだろう。
他人に感情移入をして優しくしたり、かわいそうだと助けてあげる感覚は決して悪いものではないが、この作品ではその感情が一人歩きすることで人を傷つけることがあることを教えてくれている。

作中でも、児童養護施設をテーマにしたドラマや小説でそういった”かわいそう”を助長するような描写が多いことについて触れられている。
施設の子供の中でも大人びた久志は、施設に入れていることで助かっている子供もいるのに、世の中では”かわいそう”でまとめられてしまっていることについて、達観してこんなことを言っている。
「ニーズがないじゃん、施設育ちでかわいそうじゃない子供なんて」
悪意から生まれた感情ではないにせよ、結果的に世間が児童養護施設に対して潜在的に求めているニーズは、かわいそうな子供の存在なのかもしれない。
まったくもって糞みたいなニーズだが。

ワイドショーとしての作品
これはワイドショーと同じ理論だ。
例えば、大学生が留学先で凶悪な事件に巻き込まれたとする。
ワイドショーで報道されるその大学生は
必ず、夢あふれる大学生だったり、
必ず、明るく活発な大学生だったり、
必ず、友達も多くて素敵な大学生だったりする。
当然、事実も含まれていることに間違いはないのだろうが、過剰に美化して報道する番組があるのも間違いない。
視聴者から見て、被害者は素敵な人間の方が感情移入されやすいということを制作者はわかっている。
被害者は希望に満ち溢れた素敵な人間である方がニーズがあるのだ。
見たいものを見るのが人間だから、仕方ないのだろう。
でも、この作品を読んでいるとそのニーズにぶつかっていく印象を受ける。
”かわいそう”の一言でまとめられるような簡単な問題じゃないんだぞ!
と、ファイティングポーズをとっているような気がするのだ。
この小説は”かわいそうな施設の子供”というニーズに真っ向から立ち向かっている小説のように感じる。

”かわいそう”で終わるかどうか?
胸に刺さった作中の言葉で、以下のようなものがある。
子どもたちを傷つけるのは親と一緒に暮らせないことよりも、親と一緒に暮らせないことを欠損と見なす風潮だ
これもある種の偏見で相手を”かわいそう”だと断定して接することで、自己満足を得られるし、相手を勝手に下に見ていることになる。
”かわいそう”という言葉は時に一方的な暴力と化すことがある。
相手をかわいそうだと憐れむのは、人間が持つ想像力のなせる業で、その感覚自体に罪はない。
罪はないが、その感覚の後に実際に調べてみたり寄付をするといった行動を起こすかどうかで、大きな違いが生まれるのも事実だ。
”かわいそう”で止まってしまうと、相手を憐れんでおしまいになってしまう。
”かわいそう”から一歩踏み出すと、相手の為に行動を起こすようになる。
もちろん一時期のタイガーマスクのランドセル騒動などのように、流行りのように一時のブームではいけない。
その行動は、自分がしたいことをして満足するのではなく、それこそ相手がして欲しいニーズに答えるような支援であることが望まれるのだろう。
それでも、まぁ、行動に起こしてくれること自体が嬉しくないはずはないのだが。

最後に
人によってはこの作品をどっしりとした重みがない作品としてとらえる人もいるかもしれない。
それはそれでいいと思う。
僕が感じているこの作品の一番素晴らしい点は、テーマに対して感動やリアリズムに比重を置きすぎることなく、読みやすさやエンターテイメント性を失っていないところだ。
児童養護施設の現状をもっと正確に表現している作品や資料はきっと他にももっとあると思うが、結局読んでもらわなければ意味がない。
読みやすくて楽しめる作品を多く描いている有川浩という作家が、このテーマを扱うことに何よりも意味があるのではないかと、僕は思うのだ。