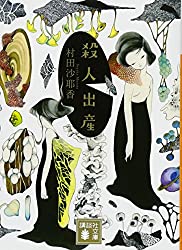
『コンビニ人間』で芥川賞を受賞した村田沙耶香さん。
その村田沙耶香はクレイジーであると、以前作家の加藤千恵さんがラジオで話していた。もちろんそれは冗談半分なのだろうが、確かに村田作品を読んでいると「コイツはクレイジーだぜHAHAHA」と思う場面は多いかもしれない。
しかし、不思議なことに村田作品を読み続けていると、本当は世の中がクレイジーなだけで村田沙耶香はピンとまっすぐ立っているだけなのではないかと感じてしまう瞬間がある。それは不条理であり得ない世界が描かれているはずなのに、その世界の一部には圧倒的なまでの真理が存在している為、ついそちらの世界へ引っ張られてしまうからなのではないかと思っている。
今回はそんなクレイジー村田沙耶香のクレイジー作品『殺人出産』のネタバレ感想・紹介を書いていきたいと思う。お付き合いいただきたい。
殺人出産
あらすじ
「産み人」となり、10人産めば、1人殺してもいい―。そんな「殺人出産制度」が認められた世界では、「産み人」は命を作る尊い存在として崇められていた。育子の職場でも、またひとり「産み人」となり、人々の賞賛を浴びていた。素晴らしい行為をたたえながらも、どこか複雑な思いを抱く育子。それは、彼女が抱える、人には言えないある秘密のせいなのかもしれない…。三人での交際が流行する、奇妙な世界を描いた「トリプル」など、短篇3作も併録。普遍の価値観を揺さぶる挑戦的作品集。
表題作『殺人出産』は、かなりぶっ飛んでる設定の作品。人口の低下が危惧される100年後の未来に「産み人」と呼ばれる存在になって10人の子供を産めば、1人の人間を殺しても良いという社会常識が生まれている世界の話が描かれている。
それは“殺人出産制度”と呼ばれ、その制度が認められた世界では『殺人』という行為の価値が変わり「産み人」はもちろん、殺される側の人間も「死に人」と呼ばれ崇められる。そんな世界で主人公・育子は“殺人出産制度”に否定的な会社の同僚・早紀子と、自らの殺人衝動を自覚して「産み人」になった育子の姉・環(たまき)を引き合わせる…。ありえないようでどこか現実的に感じられる世界の果てに、読者である僕たちの感情は果たしてどのようなものになるのだろうか?
他に『トリプル』『清潔な結婚』『余命』という3作の短編も併録されおり、どの作品も今の常識の外にある物語がリアルに描かれている。
全体の感想
常識や普通の価値観がひっくり返る世界を描いている点では『廃墟建築士』などで知られる三崎亜記作品に似た印象を受ける。荒唐無稽なようで理にかなっており、ありえないようで現実的に物語が展開する。その話の展開は突飛で感覚的に受け入れがたい描写も多いので人によっては「ありえないでしょ、そんなの」と、シャッターを閉じてしまう人もいるかもしれない。
しかし、この作品に関しては「ありえない」という感想をいうべきではないと思う。何故なら“ありえる・ありえない”というのは、現在の常識の延長にある感覚であって、その常識が壊れた世界を描いているのであれば、現在の僕たちに“ありえるかどうか”を判断するすべなどないからだ。
つまりこの作品は“現在の常識が壊れた世界”をテーマにした作品という事になる。そしてその現在の常識を壊す為のツールとして登場する二つのキーワードが、“殺人出産制度”と“蝉スナック”ということになるわけだ。ちなみに蝉スナックについては後述させてもらう。
ただ唯一気になるのが、人口の減少が問題なのであれば出産をして人口を増やしたことへの代償は、殺人ではなく金銭等の生活の安定になるのではないかと思う。人口の低下が嘆かれている中で殺人を許容する矛盾はやや感じてしまう。
殺意について
よくサスペンスでも登場する“殺意”という言葉。様々な創作物で登場する、むしろ登場しすぎる言葉なので改めて考えもしなかったが、この作品を読んでいると、そもそも“殺意”とはなんだろうかと考えさせられる。
作中では育子が姉の環と殺意について語りあう場面がある。
10人も子供を産んで10年かけて殺意を成就させようとする姉の殺意を“本物”の殺意。たまにこいつ殺したいなと思う程度の自分自身の殺意を“偽物”の殺意と話す主人公の育子に対して「殺意に本物と偽物があるとは知らなかったわ」と、からかうように姉の環が答える。
確かに思う。殺意に“本物”と“偽物”の境界なんてあるのだろうかと。相手を殺そうとする意志が一瞬でも芽生えればそれは殺意と呼べるのかもしれない。
実際に作中では育子が「いざとなったら相手を殺すことが出来る」と心の中で思う事でストレスを乗り越える描写がある。それは実際に行動には起こさないものの、その殺意を“偽物”と言い切れる根拠はどこにもないのではないだろうか。存在するのはそれを行動に起こすタイミングや環境があるかないかの、その一点だけなのかもしれない。そう考えると、僕は他人と接するのがこの上なく怖く感じてしまう。
蝉スナック
作中には象徴的な存在として『蝉スナック』というものが登場する。スナックとついているが要するにただの蝉だ。主人公の姪っ子が今流行っていると言いながらこの蝉スナックをバリバリ食べている場面がある。この『蝉スナック』なのだが、どのような意図を持って登場させたのだろうか?
一つは、蝉を食べるという行為を通して、読者に“生理的な嫌悪感”を引き起こさせるための道具なのではないかと思う。『蝉スナック』が流行して受け入れられている世間というものを読者が見て、感覚的に異常な世界であると感じさせる為のツールとしての存在意義だ。
もう一つは“早紀子の存在をブレさせる道具”としての存在意義ではないかと思う。この世界の異常性は『殺人出産システム』と『蝉スナック』の2点に特化して描かれている(実際はもっとあるのかもしれないが)。早紀子はそんな世界の中で殺人出産システムに関して完全否定をしていた為、読者から一番感情移入されるべき存在のはずだ。
しかし、最後の場面で早紀子が殺害され、胃の中から蝉スナックが出てきたことで、『殺人出産システム』は否定するが『蝉スナック』は受け入れている早紀子という曖昧な存在が誕生する。この世界の異常性を唯一否定する存在だった早紀子が、その一部を受け入れている事になる。
それは、絶対的な常識や価値観なんてものは存在しないということを表現しているのではないだろうか。存在するのはサイクルの長いブームでしかないという皮肉を描いているように思えるのだ。この作品の伝えたい点は、その常識や価値観の危うさなのではないかと思う。
『トリプル』
表題作以外の小編についても書いていこう。
2人ではなく3人で交際することが常識になりつつある世界を描いた作品。“なりつつある”という表現を使ったのは、2人で付き合うことが常識と思っている親の世代もいて、お互いにその常識の違いを疎ましく思っているという常識の転換期が描かれているからだ。
ちなみに3人とは男女男でも女男女でも良い。なんだったら男3人でも良かったりするので、性別を超越した交際ということになる。作中で特に注目して読んで欲しいのは、3人で行う性行為が描かれている点だ。
一人が受けになり穴という穴を責められる様子が描かれるのだが、その描写がエロティズムに溢れている。僕は実際、電車移動中に会社の同僚の横で読んでいたら「官能小説読んでるの?電車の中では控えたら?」とCoolに声をかけられたくらいだ。マジCoolだった。冷ややかすぎる。
『清潔な結婚』
性別のない結婚。つまり、夜の営みと結婚を切り離して考える夫婦が登場する作品。
性別を超えて一緒にいて過ごしやすいパートナーと暮らすので、逆にそのパートナーと性的なことをしようとする事に生理的嫌悪感を覚えるという設定。ゆえに生理的嫌悪感を感じずに子作りをさせるベンチャー企業が登場したりする。新しく面白い発想だが、やはり自分の感覚からすると変わった世界だなぁと感じてしまうのは、ある意味では自分自身が正常で安心してしまう。
『余命』
医学の発展で人が死ななくなり、自分の意志で死のタイミングを選択する世界を描く作品。
確かに寿命が延びれば伸びるほど、自分の死のタイミングを自分で決定する可能性が増えてくるかもしれない。それは絶望によるものかもしれないし、悲しみによるものかもしれない。もしくは単なる飽きによって死を選ぶことも起こりうるかもしれない。すべての話の中で、一番起こりうる可能性の高い世界に感じた。ショートショートなのでサクッと読めるのも魅力の一つ。
最後に
この作品の中で一番狂気を感じる場面は表題作のラストシーン。
育子と環の姉妹2人で早紀子を殺害する時に、早紀子のおなかの中に生まれる前の小さな命がいたにも関わらず、その子供を殺害し、2人で殺人が正しいことだと確信しつつ感動している瞬間だ。思わずその描写に対する生理的嫌悪感で自分の表情が歪むのがわかった。
歴史では現在常識とされる世の中の価値観なんていうものは、簡単ひっくり返ってきた。過去の成功も現在の失敗として捉えられることがある。
今この瞬間から100年後では、きっと、今生きている人間のほとんどが入れ替わり、新しい人間たちの新しい世界が広がっていくはずだ。入れ替わった後の人類が、どのような世界を創っていくのかをこの作品を読んだあとに想像すると、僕は恐怖を感じてしまう。
